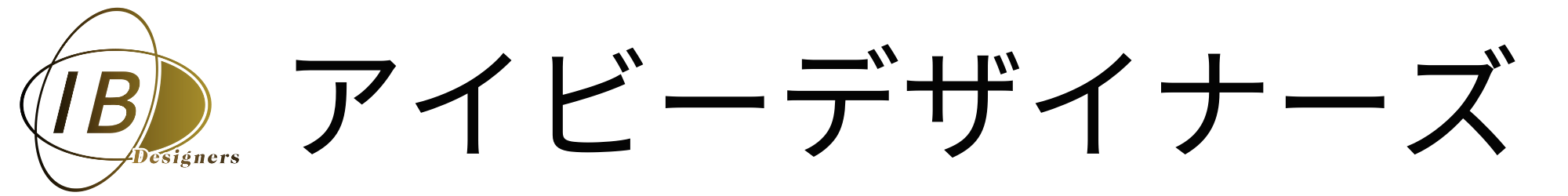【教材完成】新事業機会の発見・発掘方法
<様々な事業機会発掘方法を伝授>
企業の置かれている状況、経営方針などにより求められる事業内容は異なってきます。結果、その事業機会を発掘する方法も異なります。事業機会発掘方法には様々な方法があり、その中から当該企業に合った適切な方法を選択する必要があります。本教材では様々な事業機会発掘法を伝授するだけでなく、それぞれの発掘方法と企業の目指す方向性との整合についても解説します。尚、ここで伝授する方法はブレインストーミングなどの効果の薄いアイデア発想法ではありません。ハードワークを強いる本格的、実践的な方法です。
【教材完成】利益増加・新市場を創造する技術マーケティング
<技術を利益増加、売上増加、新市場創造につなげるマーケティング方法を解説>
多くの技術者・研究者は、技術は得意で深く理解していますが、「技術をビジネスとして成果を出せない、利益に繋がらない」、「新規市場の開拓をしたいが、そのノウハウがなく技術を持て余している」、「市場リサーチの考え方や手法など具体的な方法がわからない」、「技術担当とマーケティング担当間の連携が上手く行かない」などの課題を抱えています。世界最先端の技術開発やAIエンジニアリングをしながら常に新事業開発や社内業務改革を進めた経験から本教材を作成しました。技術を売上利益や新事業開発につなげる技術マーケティングおよび事業機会発掘方法を伝授します。
【教材完成】ゼロから始めるビジネスモデルの作り方
<ビジネスモデルの作成手順を解説>
ビジネスモデルの設計手順をご存じですか。もし知らないようでしたら、ビジネスモデルというものを正しく設計することは非常に困難です。具体例を用いてゼロからビジネスモデルを設計していく手順を丁寧に解説します。尚、本教材の前に「ビジネスモデルの本質理解とその分析方法」は受講しておいてください。
【教材完成】ビジネスモデルの本質理解とその分析方法
<成功するビジネスモデルを設計するために必須なビジネスモデルの本質を解説>
ビジネスモデルとは単なるビジネススキーム、マネタイズスキームのことではありません。
ビジネスモデルを真に理解している人材は、文系・理系を問わず少ない。そのため「新規事業開発が上手くいかない」といった状況が多く生じています。ビジネスモデル関連の書籍はスキームを整理したもので辞書としての役割に留まり、これだけでは明らかに不十分です。スキーム理解はビジネスモデル理解のほんの一部に過ぎません。本教材は幾つかの事例を通してビジネスモデルの分析方法および本質理解を目的としています。本教材により、①事業の本質とキーファクターを理解できるようになり、既存事業に対してインパクトの大きい改善策を立案できるようになる、②新事業開発において、自ら成功するビジネスモデルを設計できるようになります。
【教材完成】後発参入における採用戦略と経営層が求める説明項目
<後発参入でも市場確保できる戦略とそれを経営層に意思決定させるために必要な項目を解説>
企業の成長方法には、既存事業の更なる拡大、ゼロイチに近い新規事業開発、後発参入などがある。特に後発参入はニーズが顕在化し、市場が既に形成されているところへの参入であり、未踏に挑むゼロイチの新規事業開発で頻繁に起こる「ニーズがなかった」というリスクがない点が最大のメリットである。ここではM&A手法については省略し、自力で後発参入する事業開発を提案する際に経営層が求める説明項目と説得の仕方について解説します。
【教材完成】新規事業テーマを社内で通すための経営層への説明ポイントと数値の示し方
<経営層が新規事業テーマに期待し説明して欲しいことを解説>
技術開発部門のメンバーは技術の新規性や先進性に魅力を感じ、それに没頭してしまう傾向があります。また技術開発部門は地理的に本社経営から離れた場所に施設があることがほとんどであり、コーポレート部門メンバーと会話することも少なく、経営層の声などが伝わりにくい日常環境にあります。経営層からの声としてはCTOの年度初めの挨拶くらいです。その結果、会社が期待する新規R&Dテーマを立案することも容易ではなく、またそれを通すため経営層に何を説明すればよいのかもあまりわかっていない現場研究者がほとんどです。技術企画部門でプロジェクトマネジャーとして、各技術開発部門から精鋭110名を選抜し、11タスクフォースを組成・マネジメントし、経営層向けに技術経営に根差した技術戦略および中期技術開発計画策定した経験から「新規R&Dテーマの経営層へ向けた説明ポイントと数値の示し方」を伝授します。
【教材完成】「ニーズがなかった!」とはならない、売れる商品・サービスの作り方
<売れる潜在ニーズを掘り起こし、商品まで仕上げる方法を解説>
スタートアップでは事業成功の生命線として認識されているPMFを企業における新事業開発においてしっかりやっているケースは乏しい。理由はPMFが事業成功のために通過しなければならないステージゲートであるにも関わらず、PMFの重要性の理解が不足しているからです。新事業開発の成功に不可欠なPMFを正確に理解していただくこと、一方でPMFだけでは事業は成功しないことを解説します。またスタートアップでは数人のメンバー全員でPMF実現に注力しますが、分業化が進んだ大企業においてPMFを実現するには組織面で重大な課題があります。その課題を克服する方法も解説します。本教材により、PMFの位置づけとその重要性、実施方法を理解して頂き、新規事業の成功確率を高めて頂くことを目的としています。
【教材完成】新事業開発成功までの全体プロセスと重要成功ポイント17
<ビジネスアイデア創出からローンチさらに黒字化までにやるべきプロセスと成功ポイントを解説>
企業において新たな収益の柱を作るべく新事業開発が活発化しています。しかし過去に新事業開発を経験した者が企業内に少ないため
「新事業開発のリーダーを任されたが、具体的に何をどうしたらよいかわからない」
「新事業開発リーダーに求められる知識やスキルがわからない」
といった課題を抱えがちです。また管理者側も、今まで新事業開発の経験がなく、
「具体的にどのような助言や支援をすればよいのかわからない」
といった壁に直面しています。
このような悩みを解決すべく、新事業開発のフェーズごと(スタート段階、事業構想段階、リアルな価値創造段階、テストマーケティング段階、経営層の事業化意思決定段階、事業化後)に新事業開発リーダーが何を理解し、何をすべきなのかを学び、スムーズに新事業開発に取り組めるようになっていただくことを目的としています。 具体的には、「新事業開発リーダーに求められるミッションや戦略的思考とは何か」「構想から顧客創造し、経営層の意思決定を勝ち取り、事業化に導くコツは何か」といった点を解説します。枝葉末節のテクニカルな話ではなく、新事業開発における「正攻法と成功ポイント」を伝授します。
【教材完成】新事業開発で必要なマーケティング
<単なるアンケート調査ではない事業創造に必要なマーケテイングを解説>
現在の新事業開発は、「潜在ニーズを発掘し、誰よりも早く事業創造し、一気にオンリーワンの立場を確保すること」が主たる成功要因です。しかしアンケート調査、ヒアリングなどは潜在ニーズ発掘には効果が期待できません。潜在ニーズとは「顧客自身も認識していないニーズ」ですから、質問しても何も出て来ません。本教材では「顧客自身も認識できていないニーズ」を見つけ出すマーケティング方法を伝授します。
【教材完成】CTO必須の経営層を感動させる技術戦略・中期技術開発計画策定方法
<新規事業開発のプロからの視点で技術戦略・中期技術開発計画策定方法を解説>
技術開発部門のメンバーは技術の新規性や先進性に魅力を感じ、それに没頭してしまう傾向があります。また技術開発部門は地理的に本社経営から離れた場所に施設があることがほとんどであり、コーポレート部門メンバーと会話することも少なく、経営層の声などが伝わりにくい日常環境にあります。経営層からの声としてはCTOの年度初めの挨拶くらいです。その結果、会社が期待する新規R&Dテーマを立案することも容易ではなく、またそれを通すため経営層に何を説明すればよいのかもあまりわかっていない現場研究者がほとんどです。技術企画部門でプロジェクトマネジャーとして、各技術開発部門から精鋭110名を選抜し、11タスクフォースを組成・マネジメントし、経営層向けに技術経営に根差した技術戦略および中期技術開発計画を策定し、経営層を感動させた経験から技術戦略・中期技術開発計画策定方法を伝授します。
【教材完成】競争優位戦略特講
<ビジネスモデル研究家として競争優位戦略の構築方法を事例を交えて解説>
競争優位戦略は事業の継続性において大きな要因です。これを秀逸にしておかないとあっという間にレッドオーシャンとなり、シェア低下、利益率低下、事業撤退という憂き目にあってしまいます。新事業開発のローンチ自慢で終わるので良ければ競争戦略は不要ですが、本物の経営者はその事業を何十年も継続して儲かるように仕組みを構築します。秀逸は競争優位戦略を構築している事例を10以上解説し、競争優位戦略の要諦を理解して頂くこと、競争優位戦略を設定できるようになって頂くことが本教材の目的です。
【教材完成】知的財産戦略および知的財産中期計画の策定方法
<新規事業開発のプロからの視点で知的財産戦略および知的財産中期計画の策定方法を解説>
新規事業開発を30年間やってきたプロが、知財部門で5年間実務をやった経験から、会社と事業に大きく貢献する知財戦略および知財中期計画とはどのようなポイントを押さえたものであり、どのようなプロセスで策定していくのかを伝授します。本教材の前に「CEOおよびCTOが知っておくべき知財の本質」の受講が必要です。
【教材完成】CEOおよび経営企画部が知っておくべき経営戦略および中期経営計画の策定方法
<新規事業開発のプロからの視点で経営戦略および中期経営計画の策定方法を解説>
新規事業開発のプロ、かつ戦略系経営コンサルタントの視点で会社および事業成長、組織育成、財務健全化などの軸のしっかりした経営戦略および中期経営計画の策定方法を伝授します。
【教材完成】CEOおよびCTOが知っておくべき知財の本質
<新規事業開発のプロからの視点で知財の本質をビジネスおよび経営の視点で解説>
新規事業開発を30年間やってきたプロが、知財部門で5年間実務をやった経験から、会社と事業に大きく貢献する知財とは何か、知財ポートフォリオとそのアップデートの意義はどのようなものなのか、会社全体の中での知財とは結局何なのか、という幹の部分を中心に解説し、合わせて枝葉末節も補足解説します。
知財部門は弁理士を中心とした専門家集団であるため権利化、先行技術調査、クリアランス調査、侵害訴訟対応などの枝葉末節の実務が中心で幹を理解できていないことがほとんどです。経営トップは自ら幹を理解する必要があるのです。
【教材完成】事業化を目指す技術開発契約(NDA、委託開発、共同開発、実施契約等)の重要ポイントと交渉術
<新規事業開発のプロからの視点で俯瞰的、戦略的に解説>
研究者、技術者であっても事業化まで目指したり、スタートアップを起業する場合には、相応の交渉力がなければなりません。交渉の中でも契約書までに至るものこそ本当に重要な交渉です。この重要な交渉で成功するために必須な知識スキルを伝授します。
新規事業開発のプロの視点を持ちつつ、さらにオープンイノベーション支援の立場から大企業で知財部門のリーダーとして毎年1000件近い契約案件の審査実務経験からのノウハウです。
【教材完成】新規参入検討分野における事業機会発見・発掘法
企業の成長方法には、既存事業の更なる拡大、ゼロイチの新事業開発、後発参入などがある。特に後発参入はニーズが顕在化し、市場が既に形成されているところへの参入であり、未踏に挑むゼロイチの新事業開発で頻繁に起こる「ニーズがなかった」というリスクがない点が最大のメリットである。一方で既にレッドオーシャンとなっている市場への参入であり、そこで有望な新たな事業機会を見出すことが生命線であるが容易ではない。本教材では、後発参入での有望な事業機会の発見・発掘法とそこまでのプロセスを含め伝授します。
【教材完成】ビジネスモデル設計特講
秀逸なビジネスモデル設計方法を解説します。これを習得することにより
・競合他社に勝てる
・顧客満足度が向上する
・利益率が向上する
・売上とシェアが拡大する
・事業のレジリエンスが向上する
などの効果を手にすることが出来ます。
【教材完成】戦略特講
戦略を正しく理解できている社会人は1%以下です。理解できているのは優秀な創業社長くらいです。本特講で戦略の本質を理解し、それをデザインするスキルを身に着けることで
・会社業績が向上する
・組織パフォーマンスが向上する
・人生のパフォーマンスが向上する
など幅広くその効果を手にすることが出来ます。
【新コンサルティングメニュー】既存事業のビジネスモデル健康診断サービス
皆さんが入社したとき存在していた既存事業は洗練されルーティン業務となっていることがほとんどです。その結果、誰も疑問を持たずに粛々と業務に取り組んでいます。一方、時代は進展し変化し続けており、いつの間にか時代遅れのビジネスモデルとなり、競争力が衰え収益力が低下あるいは成長が鈍化している可能性があります。
この誰も疑問を持たず放置されている既存事業のビジネスモデルの健康診断を、新規事業開発専門家でありビジネスモデル研究家が実施し、現在あるいは未来に適合できるビジネスモデルにアップデートあるいは革新するサービスです。