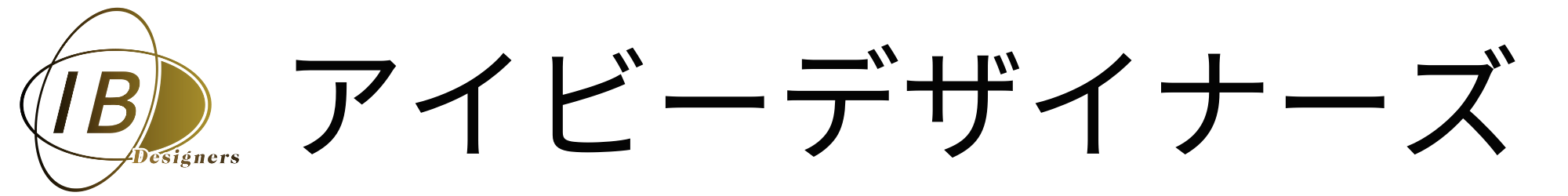【マネジメント】会社でのAIとの付き合い方①

生成AIは調査スピードの早期化、画像作成の早期化など主にフリーランスの方に多くの便益を提供しました。
会社勤めの方には一部のホワイトカラーの方に調査という部分で省力化に貢献しました。そのため会社組織としての便益としてはまだ軽微なものです。これらのAIは人間の仕事の一部分を手伝ってくれるという程度のものです。
しかし推論モデルが急激に進展し、対話型でAI自身が単独でタスクを完遂させることができるAIエージェントが登場するという前提を立てると、AIとの付き合い方が根本的に変わってきます。
AIエージエントにあるまとまった仕事をすべて人が介在することなく完遂まで任せることが出来る(全自動化)のであれば、AIエージェントができるタスクはすべてAIに任せ、それ以外の仕事を人間が実施するという役割分担となります。
結果、業務プロセス全体をAIエージェントを中心に再設計する必要があります。さらにAIエージェントは常に進化していくため、現時点ではAIに任せられない仕事でも数年後には任せられるようになります。
そこまでの長期的展望を見据えて業務プロセスを再設計する必要があります。具体的には、全体業務プロセスを適切なサイズのモジュールに分解し、モジュールごとにAIに代替させるか、まだ人間がやるかを決めるという骨組みにします。
この方法であれば、AIエージェントが発展し、実施可能なモジュールとなったものを逐次、置き換えていけばよいのです。柔軟性、受容性をAI導入を前提に高めておくのです。
またAIおよびAIエージェントにやってもらう仕事で大きな効果があるのは、365日24時間働く必要のある業務など人間が長時間かけて実施している業務です。週に数時間しかやらないような業務をわざわざコストをかけてAIに代替させてもコストメリットはありません。
何でもAIという風潮をAIベンダーは流布していますが、AIを妄信するのではなく、ユーザー目線で厳しくその価値を評価した上で導入してください。
価値の低いAIは導入する必要はないですし、逆効果となります。経営層もAIという旗振りで満足するのではなく、「本当に役立つAIのみを導入する」というガイドラインを策定する必要があるのです。