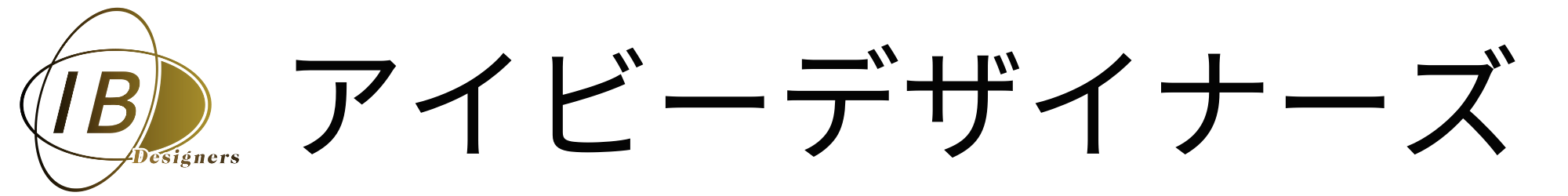【新規事業】差別化戦略の崩壊事例

競争優位戦略の中に競争を回避する差別化戦略があります。
例えば、競合製品にはない「オンリーワンで顧客が望む機能や品質」を付加価値として持っている商品です。
コメで言えば、「コシヒカリ」「つや姫」などです。同じコメであっても「その美味しさに特徴を持たせ差別化した商品」です。このようなお米は、高級料亭、寿司屋で特に取り扱われますが、一般消費者であってもコメにこだわりをもつ家庭ではこれらを購入します。他の米より2割程度高くてもです。このような時代が1年前までは長きにわたり続いていました。
しかし昨年後半から今年にかけコメの平均価格が2年前の2倍以上となりました。今までは2000円の標準価格に400円程度プレミアム料金を支払ってコシヒカリなどを購入する消費者が多くいました。400円多く払って美味しいお米が食べられるのであればそれほど躊躇なく購入できていました。
現在のお米の標準価格は4400円程度です。以前のコシヒカリ価格の2倍弱であり、さらにこれにプレミアムを払うと5000円超になります。
消費者の実質的な収入はそれ程増えていません(物価が上がり、さらに消費税も物価が上がった分だけ多く取られます)。支払能力は高まっていないのです。
コシヒカリなどのブランド米は高嶺の花となり、もはや購買対象から消えています。その結果、従来まで成功していたブランド米というプレミアムを払いこともなくなり、差別化戦略が崩壊しています。端的に言えば、高いコメは売れないのです。消費者ニーズと大きく乖離してしまったのです。
この付加価値を消費者が受け入れられなくなった現在、ブランド米も価格競争に晒されています。結果、ブランド米と普通の米との価格差はほとんどなくなっています。
丹精込めて品質改良し作り上げてきたブランド米のその価値を価格に乗せることができず、投資対効果としては低下しています。
以上の事例から言えることは「差別化(プレミアム)」というのは「消費者の支払能力内」の相場のときだけ有効に機能するが、支払能力を超えた途端にその機能は無効化されてしまうということです。
外部環境変化(特に相場)により競争優位性のロジックが変わってしまうということを理解しておく必要があるのです。